 外国語
外国語 ラテン語さん著「ラテン語さんが教える 外国語上達への学習法」の感想。
一般的な外国語独習法というよりも、ラテン語さん自身の外国語学習法を紹介した本。ラテン語はもちろん、9カ国語にわたる学習歴から取り出された方法はどれも役に立ちそうなものばかり。入門書の選び方、単語の覚え方、学習環境の整え方など。9カ国語それぞ...
 外国語
外国語  外国語
外国語 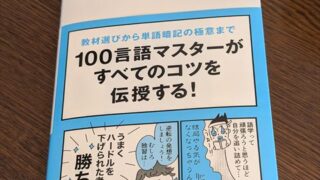 外国語
外国語 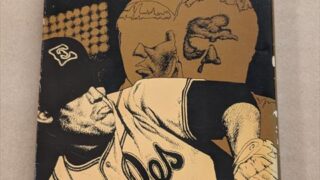 本
本 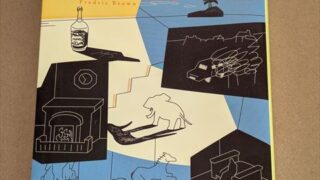 本
本  本
本 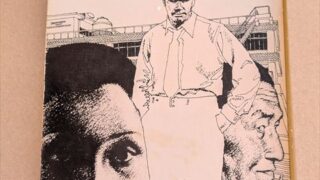 本
本 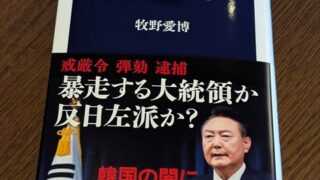 本
本  本
本 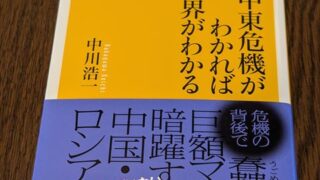 本
本