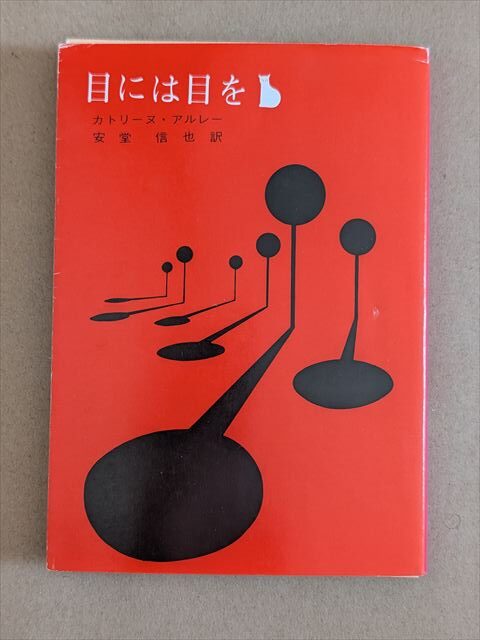
4人の男女の独白によるミステリー。登場人物は、青年実業家ジャンとその妻アガット、友人で富豪のマルセルと病弱な姉の女医マルト。4人はそれぞれの思惑を抱きながら家族ぐるみの交際を始める。しかし根本は愛と欲。打算に裏打ちされた胸の内がつづられ、事件へと結びつく。
男たちの思惑は単純だ。経済的支援だったり、横恋慕だったりする。しかし、女性二人は簡単ではない。貪欲に欲望を成就させようとするわけでない。偶々訪れた機会をうまく利用し、そこそこの目的を達成しようとするだけだ。そこに本能的な姉弟愛が絡んだりするので余計に複雑になる。
殺人などというものは、犯罪者にとってもある意味では聖域であり、男たちであれば相当の覚悟を持って取り組む難事業だろう。しかし、彼女たちにとって人の死は特別なものではなく、成り行きの思惑の中に簡単に取り込んでしまう。まるで、手駒のひとつを使うようにあっさりと。
アガットにしてもマルトにしても、根っからの悪女ではないかもしれない。それだけにこういう結末になるのは、女性の本能が持つ悪をあらわしているようで尚怖ろしい。



