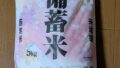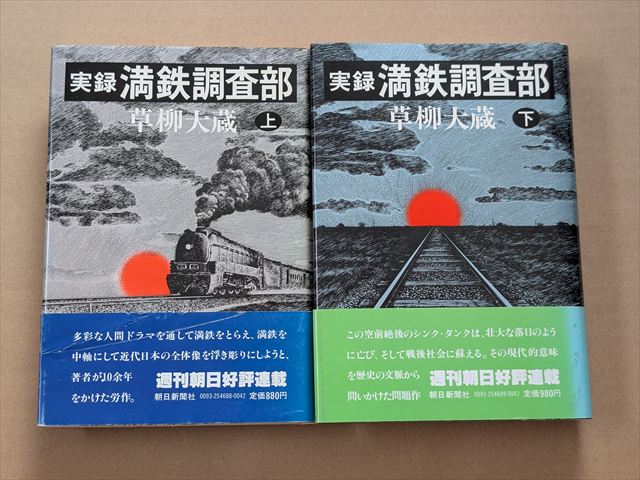
満鉄調査部についての詳細なノンフィクション。昭和54年発行。
著者の徹底した取材力には驚くばかりだ。この上下巻を書くために、どれほどの取材を重ね、どれほどの資料を読み込んだのか。巻末の参考文献は省略してあるのは、書き切れないほどの資料にあたり、一般に入手不可能なものが多数あるためだ。膨大な労力を凝縮して書き上げた本書は紛れもなく名著だ。
本書は系統的に分析するのではなく、エピソードをつなげて年代を下っていくスタイルを採っている。あまりにも詳細な記述のため、そのままでも網羅的な年代史として読めるほどだ。
上巻は主に満鉄調査部の活動が描かれる。株式会社の一部門にすぎなかった満鉄調査部は、ただのシンクタンクをはるかに越えた役割を果たす。新天地に夢を求めて集まったメンバーも多種多彩だ。政治的にも右から左まで何でもありで、思想的立場など関係なく集まった俊英がたちによる自由闊達な活動が行われた。政府からの豊富な予算を背景に、日本の満州経営の中枢を担う頭脳集団として成果を出し続ける。そのため軍部にも一目も二目も置かれる存在になっていく。
下巻は満州国の建国と崩壊が主となる。満州事変以後の軍部の台頭により徐々に自由な活動が制限される満鉄調査部。この巻は満州史としても興味深い。混乱の中国側との交渉、欧米の列強との外交的な関係などが詳細に記され、満州国の実像を見るような感じさえする。
今となっては、満州国と言えば傀儡国家という色眼鏡で見られることが多い。現地の人たちを棍棒で殴りつけて統治したのではと思われがちだ。他国の領土での国家経営がいかに難しいかは、近年のイラク、アフガニスタンを見れば明らかだ。
本書に書かれている満鉄調査部が関わった事例は、紛れもなく国家経営の成功例と言えるだろう。しかし、侵略国家の成功例について、後の世で「満州経営に学べ」などというスローガンがつくられるはずもなく、歴史の中にうずもれてしまうのかと思うと残念だ。
本文中には、満鉄調査部のメンバーたちの本書執筆時点での肩書きが記されている。彼らが戦後日本のあらゆる分野に散らばって復興を支えたのは確かだ。知のユートピアであり、人材の宝庫であった満鉄調査部。改めて日本の貴重な歴史だと思う。